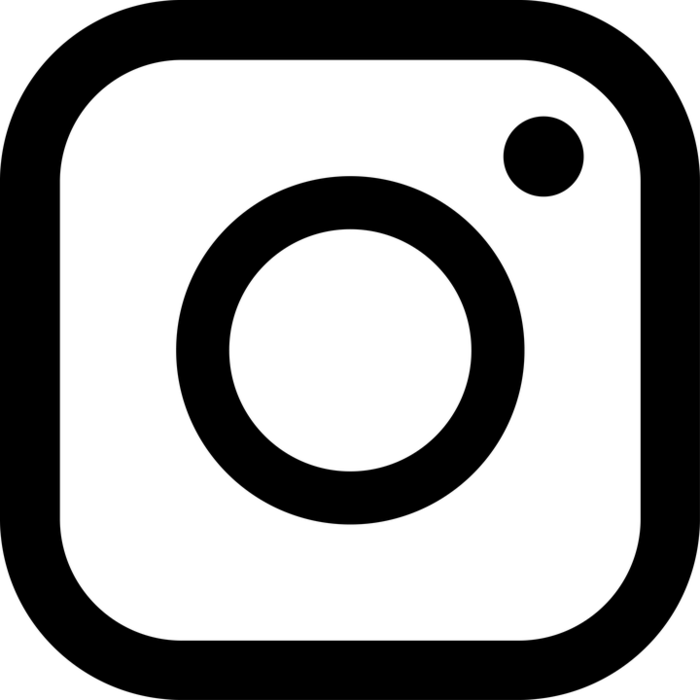星について語ろうとするとき、もしくは星についての書物を紐解くとき、どうしても実感をもってその情景を思い浮かべることができないのはなぜだろう。きっとそれは暗闇を見たことがないからだ。
野尻抱影という人についても初めて知った。明治時代に生まれ、大正、昭和にかけて星に関する膨大な数の随筆を残し、星座に和名もつける作業にも携わったという。しかし、星についての知識がない私には、彼の随筆を前にして呆然とするしかない。それでもひとつ印象に残っている彼の文章があった。それは、彼が住む東京界隈で、つい最近まで見えていた星が都市開発によって見えなくなってしまったことを嘆いているものだ。だから彼は、時折、山の向こうに赴いて、その夜の暗闇で「目を洗う」という。きっと当時の日本の夜は帰り道の星空に目を凝らしてしまうほど暗かったのだろう。星が瞬く夜空を見ることができない私たちは、しばらくの間、物語を失っている。
そういえば、私がはじめて暗闇を見たのはチリのアタカマ砂漠にいったときだ。私はその砂漠のど真ん中で、先住民の人々が暮らすコミュニティでしばらく生活していたことがある。昼間は皮膚が焼ける音が聞こえそうなほどの灼熱、夜は耳が千切れてしまいそうな極寒という湿度ゼロの砂漠地帯である。私が驚愕したのは日中の過酷な環境よりも、果てしない夜の闇だ。新月の夜はいくら眼球を突き出して目を見開いても何も見えない。暗闇はただ暗いだけではなく、ねっとりと身体全体にまとわりつくような重さがある。まるで息ができないように感じるのは、きっと身体のまわりの距離感をはかることができないからだろう。
そういうときはすぐに外に出て、空を見上げる。すると、ずっと遠くに空があることがわかって、急に呼吸が楽になるのだ。暗闇を夜空に変えてくれるのは、言うまでもなく星だ。それは銀色の砂粒を勢いよく撒いたように、空のすべてを覆っていて、よく見ると星の輝きには強弱があるからか、銀色の布が波打っているようにも見えてくる。私が星を見ているのではなくて、星が私を見ているのだった。そうしてずっと上を見続けていると、もう二足歩行なんてしているのが馬鹿らしくなってしまって、すぐに砂漠の冷たいビーチのうえに寝転んでしまう。
ある日、先住民の人が星の読み方を教えてくれた。彼らの星の読み方にはPhysical worldとSpiritual worldがあるという。空にはラマをはじめとした動物や狩人の姿をした人間、虫もいる。星空に蝶が現れると次の日には砂漠に雨が降るという。Physical worldは日々の生活を導いてくれる一方、Spiritual worldは人間が死んだ後の世界を説明してくれる。
「ほら、オリオンのベルトに3つの星があるでしょう。死者はそのベルトを通って、その向こうにある三角形のブラックホールのなかに連れられていく。そこまでの道筋を導いてくれるのは蛇だ」
少しばかり明るい星の連なりが、オリオンと蛇の輪郭を導いている。そうして星の点と点をつなぐと線になって、次々と絵が浮かび上がってくることを実感する。
夜空は壮大なキャンバスだ。そして劇場だ。人間が集まって生活することで飽和していく感情や出来事を抱えきれなくなったときに、人々は物語を編み出し、空に解き放ったのだろう。まるで窮屈な暗闇から解き放たれたいという思いに突き動かされるように。
私は砂漠の冷たいビーチに寝転んでキャンバスを見る。私が描きたい物語とはなんだろう。
星は暗闇があるからこそ輝いている。
この文章はTezukayama Galleryでの展覧会「星の百年」(2020年11月13日〜12月12日)への寄稿文として書かれたものです。