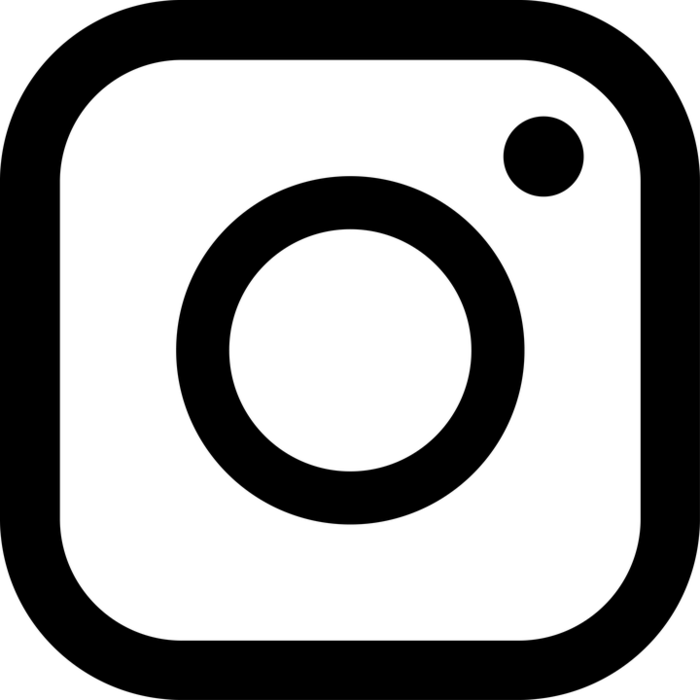ポルトの太陽は霧の向こうから柔らかく街を包む。宿がある住宅地から街の中心街に向かって歩くと自然と坂を下っていて、道にしたがっているうちに最後にはドウロ川のほとりに導かれる。ポルトガルは北部の街、ポルトはこの豊かな川岸から坂を上がっていくようにできていった街で、歩けば歩くほど空に近くなるような感覚に襲われる。
歩いていると時折、窓が開いている家がある。正確には窓が開いているというより、雨戸が開いている家だ。ポルトガルの家は道に沿って建物のファサードが直立していて、しかもどの家の壁もそれぞれ個性的で色鮮やかなタイルでできているので、その色と模様の連なりを感じながら歩く。しかし、どの道ももう何百年も変わっていないような石畳でできていて、人がやっとすれ違うことができるほどの幅の狭さなので、本当に家のファサードに寄り添うように歩くことになる。
そんな様子なので、1階の家の窓が開いていると家のなかが丸見えだ。ソファーにもたれかかるように座りながら、テレビを煌々とつけてサッカーを見ている家。なぜか、テレビを見るときは部屋の中がめっきり暗いので、外からはサッカーのボールが転がるようすまで見える。もしくは窓際に食卓がある家。赤いチェックのテーブルクロスがかけてあってその上に一輪の花がさしてある。老夫婦が食卓について、スープを口に運ぼうとしている。
窓の中には親密な世界がある。たった一枚のガラスを隔てた向こう側に見えているけれど、入り込むことができない場所。街を歩いていると、そんな光景がポツリポツリと目のなかに飛び込んでくる。

ポルトの窓 
アムステルダムの窓
そんな光景を見るのはポルトガルだけではない。オランダのアムステルダムの運河沿いを歩いていたときのこと。やけに傾いた建物があるな、と目の前の建物を見ていると、アーチ状の窓の向こうにコーヒーカップを手に持つ男性の上半身が見えた。それにしても、なんと窓の大きなことか。なんでも、アムステルダムは土地が狭いから、細長い建物を建てることが当たり前で、しかもそのせいで室内が暗くなってしまわないように窓を思いきり大きくする。しかも、カーテンをしている家がめっぽう少ないものだから、背の高いオランダ人が窓の向こうを闊歩しているのが丸見えだ。こちらも目のやりどころに困る。
新しい街を歩いた時の感覚はその街に慣れてくると、幻のようにふっと消えていってしまう。だけど一度感じた街の印象を、時間と距離を置いて振り返ってみると、その時には考えても見なかったようなことを思いついたりする。ふと、そんなことを久々に再会したアメリカ人建築家のクインに話してみることにした。彼女ほど、世界中の街を意識して歩いている人はいないからだ。.
「そうよね、ヨーロッパの街って窓の向こうが丸見え。でもね、ヨーロッパではみんなこう思っているっていうの。you are not supposed to look at it」
ヨーロッパの人々が丸見えの窓の向こうにわざと目を向けないようにしているというようすを想像すると、なんだかおかしい。混みいった場所に住む人々の掟のようなものなのだろうか。あけっぴろげのプライベートスペースを外から見ないようにする文化があるのならば、空間を締め切ってしまう壁なんていらないのかもしれない。
クインは大学院の博士課程に所属しながら、世界中の自分が興味のある建築を見に行っている。彼女はそれをアーキテクチャー・クエストと呼ぶ。日本にもしばらく滞在していて、徳島、青森、北九州と3箇所のアーティストインレジデンスに参加しながら、時間が許す限り日本中の建築を見に行っていた。大学の博士課程にいるとつい文献を盾にしてアカデミズムの書棚を満たすことに集中してしまいがちだけど、自分がその建築を見て、どう感じて、どう思ったかをとにかく記憶しておきたい、というのが彼女のクエストのはじまりだ。
その彼女が建築を語る上で課題にしているのは「in between space」、つまり「間のスペース」。キッチンや居間や寝室など、機能を持っている部屋ではなく、部屋と部屋をつなぐ場所。もしくは内と外をつなぐ場所。
「初めて日本に来たときはとにかく驚いたわ。だって、こういう場所ないかなあ、と思っていた場所が突然日本の建築の中に現れたのだから」
私が、「土間」とか「縁側」のことね、というと彼女は大きく頷いて言った。
「そう、DOMAとENGAWA!」
それにしても、なぜ「in between space」に興味を持ったのだろうか。ベトナム系アメリカ人のクインはヴァージニア州で生まれ育ち、日本に来たのは博士課程を始めた30歳を過ぎてからだ。アメリカ南部のヴァージニアには、南部の家特有の「ポーチ」(玄関前のウッドデッキのあるスペース)のある家があるけれど、日差しから室内を遠ざけるという目的があって、彼女によるとin between spaceというふんわりとした感覚的なスペースとは少し違うようだ。おそらく機能的すぎるということだろうか。
「建築がひとつできるまで、とてつもない年月がかかるでしょう。その間に人々の意識も生活も変わってしまうわ。それならば、建築でもない、アートでもない、どのカテゴリーにも入らないスペースってなんだろうと考えたの。そういうスペースが人々に働きかけることって何だろうって」
クライアントから差し出される依頼を待っているのではなく、自分から空間に関する問題に立ち向かっていこうということである。クインは徳島県神山町という人口六千人にも満たない集落でアーティストインレジデンスをするなかで、この疑問を形にしたインスタレーションを作った。役所の駐車場の一角の原っぱに、杉の角材を使った壁と床だけでできた構造体のようなものを建てたのだ。壁は角材を等間隔に並べたルーバー状になっているので、向こうを見通すことができる。その床と壁の構造体に到達するまでのアプローチには石畳があるけれど構造体にはドアがなくて、エントランスがはっきりとしているわけではない。緩やかに廊下と居間のようなスペースがルーバー状の壁で仕切られていて、全体的に縁側だけでできた空間という印象だ。
インスタレーションとは仮設でも常設でもない、それ以前の構造物だ。建物でもアートでもない空間を問うクインが今まさに必要としている実践のひとつになったのだろう。屋外にあるけれど、床と壁があって座ることができる。床があるというだけで室内にいるような気持ちになる。なんなら、デッキの上に乗る時に靴を脱ぎたくなるほどだ。これができてから、もう2年ほどが経っただろうか、杉の角材は酸化して黒くなって時間を刻んでいる。

「in between space」という言葉を反芻しながら、再び、ポルトガルの街のことを考えてみる。アパートの窓もさることながら市街地に出てみるとウィンドウディスプレイの賑やかさが目をひく。エントランス横のガラスの向こうの壁一面に商品が律儀に飾られていて、わざわざ店内に入らないでも店の中にある商品のラインナップがわかる。肉屋ではソーセージが天井から大きさと色別に分かれてぶら下がって濃厚な赤色のグラデーションをつくり、パン屋の軒先にはトレイに並んだパンやらケーキやらが、それぞれ違う表情をしつつ正面をこちらに向けて並んでいる。お菓子屋さんではパッケージに入ったキャンディーやチョコレートが袋や箱ごとびっちりと並べられていて、遠くから見ると色とりどりのピクセルのようだ。
ウィンディスプレイは外と中をつなぐ、in between spaceだ。縁側が室内でくつろぐ人が室外を見るためのスペースだとしたら、ウィンドウディスプレイは外を歩く人が、店の中の様子を垣間見る場所だ。
今、街では携帯電話を持った人々が夢遊病のように歩いている。どこにいようと周りのものには目も向けずに、新しい自分を作ってくれるイメージで頭の中がいっぱいだ。ふと携帯から顔を上げると、ガラスの向こうに自分とその周りの建物が写り込んでいる。見慣れた顔、いつもと変わらぬ自分。そのことに気がついたとき、ガラスの向こうにあるものが急に鮮明に立ち現れ、突然、映り込みが消えてなくなる。0.1秒の出会い。その瞬間、そこには何が見えるのだろうか。店の持ち主が作った親密な空間。ウィンドウディスプレイは街の中に突然現れるガラスのポケットだ。