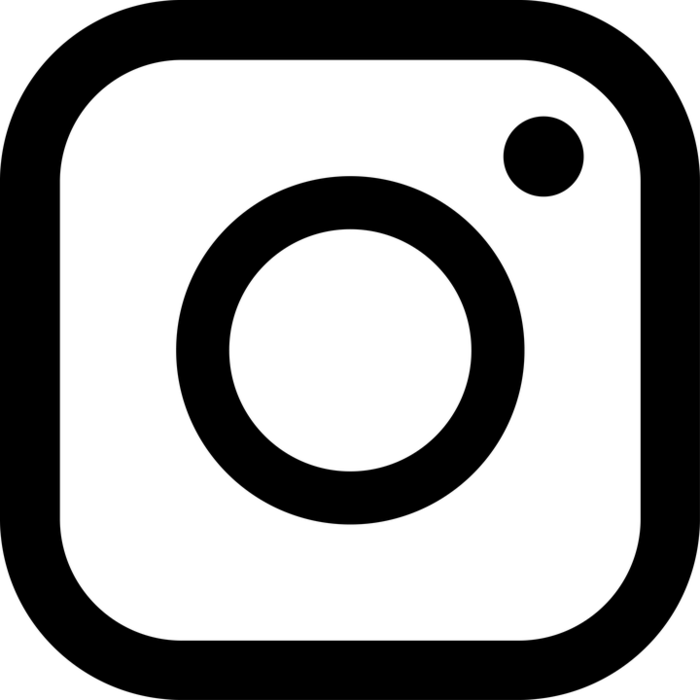2015年の夏のギリシャは何かと話題が豊富だった。経済危機だ、ギリシャが消滅するかもしれないという声もあった。いかつい顔をしたEU本部のスポークスマンが記者会見で「もうEUはこれ以上、ギリシャを支えることができない」と、思い詰めたような顔をしている。
あの神話を生んだギリシャが消滅するなんて、そんなはずがない。資本主義が生まれる前からある国だぞ。毎日、報道では「混乱」を避けて旅行客が激減しているという。しかし、そんな声をBGMに私はこの年に初めてギリシャに行った。
アテネ・エピダウロス・フェスティヴァルという芸術祭がある。1955年から毎年夏に行われている伝統の芸術祭だという。アテネと、もう一つの会場となるエピダウロスはペロポネソス半島の東側にある場所で、世界最古の劇場があることで有名らしい。古代ギリシャ時代、エピダウロスは大規模なヘルスケアセンターだったらしく、治療をする場所だけではなくて、病気を予防するためのスポーツ施設や大浴場も遺跡から発掘されている。その中に劇場があるというのは、演劇を見るということが脳のリラクゼーションの一つとして考えられていたというのだ。泣いたり笑ったりすると頭も心もスッキリする、といったところだろうか。
2015年の芸術祭の目玉は、エピダウロスの古代劇場で日本の能が上演されるということだった。そのことを聞いただけでも鳥肌が立つ。その第一情報をくれたのは、大学時代の同級生で能楽師になった川口くんだった。エピダウロスの舞台に立つのは、観世流梅若玄祥(当時、現梅若実)先生の一門だというのだ。川口くんは、大学の能サークルで能に魅了され、卒業後に一大決心をして梅若家に住み込みの書生生活に入った。20代の若者の実生活とは遠くかけ離れたストイックな修行を経て、その反動を肥やしに才能をめきめきと伸ばし、今では能楽師として数々の舞台を踏んでいる。学生の頃からの彼のミッションは日本をカッコ良くすること。日々、日本酒を片手に能の裾野を広げる活動に忙しい。私も彼の抱腹絶倒の能ガイダンスに導かれて、年に何度かは能に親しんでいた。
というわけで、古代演劇発祥の地の舞台に能楽師として立つことができるということで、川口くんは大興奮だった。そのことを聞いて私の頭のなかに、Once in a life timeというフレーズがよぎった。気が付いたときには航空券の手配は済んでいたと思う。こうして、川口くんの後輩で同じく大学の能サークルの出身の樋野ちゃんと一緒にギリシャに向かうことにした。樋野ちゃんは大学卒業後もひと時も欠かさず能を追い、見守っていて、私はそれを樋野ちゃんの「能楽パトロール」と呼んでいる。
旅の準備をしながら、そういえば、経済危機だった、と思い出した。現地では現金が引き出せないとか、強盗があちらこちらにいるとか、まだ情報は錯綜していた。しかしながら、空港を出た瞬間、そんな心配は灼熱の太陽のもとに水蒸気となって、消えていった。アテネの夏は賑やかで華やかだった。通りは観光客でいっぱいで、道端には盛大に飲み屋のテーブルが出ていた。ATMから必要なだけのユーロを引き出したと思う。特に、混乱の記憶はない。樋野ちゃんと、暑さもやわらいだ夕暮れに、野外のテーブルでふっくらとしたいかの丸焼きにオリーブオイルをたっぷりかけて食べた。デキャンタに入ったワインはそこそこ冷たくて、頭のなかが夕暮れのなかに蕩けていった。このテーブルの上では通貨なんてただの乾いた紙切れだった。私たちはアテネに数日間過ごしてから、エピダウロスに移動することにした。

薄暗いバスターミナルの人混みに揉まれて、なんとかエピダウロス行きの長距離バスに乗り、2時間ほど真っ白な荒野と真っ青な空のはざまを走った。ここが目的地だ、とバスの運転手に言われて、崖のど真ん中に降ろされて途方に暮れたけれど、そこから宿は歩いて10分ほどの場所にあった。そこがエピダウロスの劇場から最も近い場所にある宿なのだ。
演劇祭は暗くなってから始まる。日中40度にもなる夏のギリシャでは、屋外の円形劇場で座って演劇を見るなどというのはありえない話なのだ。宿のまわりはしんとしていた。劇場といえば街のど真ん中にあるイメージだけれど、どうやらここには街らしきものは一切ない。360度荒野である。不安そうな顔をしている私たちに向かって、宿の主人は相変わらず何もない荒野の向こうを指差す。ほら、君たちには劇場が見えないのか、と言っている。
夕暮れ。同じ宿に泊まっている人の車に乗せてもらってひたすら何もない道を行くと、ほどなくしてEpidaurusという文字が見えた。まさかこの砂利道の向こうが、と思いながら広大な駐車場を出ると、劇場の入り口があって、そこには場違いなほど小綺麗に整備されたチケットオフィスがあった。
古代エピダウロスの劇場は毎年の芸術祭を受け入れるために思った以上に整備されていた。入口の向こうには感じのいい野外のカフェレストランがあって、上演前の時間を過ごすことができるようになっている。そこから緩やかな坂道を上がって木陰を突き進むと、やがて視界がひらけた。ここだ、と息を飲んだ。目の前にはすり鉢状の客席がぐるりとこちらを向いていた。そのふもとには石でできた小高いステージがある。一万五千人を収容するというわりには思ったよりもコンパクトに感じのはなぜだろう。ぐるりと見渡さなくても客席全体が正面にどんっと迫ってくるのだ。ステージから見ると一万五千人分の視線が一直線に胸に飛び込んでくるような感じがした。その視線を一手に引き受けて、肥やしにできる人こそが役者なのだろう。
ステージ傍をぐるりと回って、階段を上がって客席へ。すると巨大なすり鉢状の客席は両側にどこまでも続いているように大きく、とてもじゃないけど客席の全体を把握できない。適当な席を探して座ると、自然に四角いステージを目が捉える。その視界をさえぎるものはない。左右にも前後にも広がる広大な客席は全く視界に入らない。ステージから見上げた時とは全く逆だ。つまり、役者も観客も互いをぎゅっと手中に収めているということだ。これが、ギリシャの円形劇場の黄金比なのだろうか。とんでもない求心力を身体に感じてヒリヒリした。
太陽が沈むと急ぎ足で夜がやってきた。ねっとりとした暗さがあたりを覆うと、新作能の「ネキア(冥界)」が始まった。
新作能もさることながら、私が楽しみにしていたのは能の名作「翁」と「土蜘蛛」の公演だった。暑さを避けて、夜の公演の翌日の日の出前に上演されるという。日の出とともに古代ギリシャの劇場で「翁」を舞うなんて、聞いただけでワクワクした。それこそ、一生に一度しか見ることができない特別な奉納に違いなかった。
「ネキア」は大成功のうちに終了した。夜風を受けながら、日本の芸能を初めて見た観客は不思議な余韻に浸っているようだった。公演の終了が夜の11時ごろだった。この近くには宿がほとんどないので、観客は車を2時間飛ばしてアテネに戻るか、少し離れた村の宿を取っているのだろう。そう考えると、たった数時間の睡眠で、誰が朝の演目を見に来るというのだろう。いや、もしかしたら観客は私と樋野ちゃんだけかもしれない。でも、それでもあまりあるほど翌朝の「翁」と「土蜘蛛」の公演は楽しみで仕方なかった。
翌朝5時に私たちが宿を出た時はまだ地平線もわからないほどの夜だった。朝の円形劇場の客席はひんやりと冷たかった。目をつぶっても、目を開けても暗闇だった。眠さと戦いながらも、なんとか劇場にたどり着き、客席に座っていると、しばらくしてポツリポツリと人が入ってくる気配を感じることはできた。朝だからか、みんな必要以上に声を潜めてゆっくりと移動している。
人の声が少しずつ大きくなっているのに気がついて、ぼうっとしていた頭を奮い立たせる。太陽の光があたりをぼんやりと明るくしはじめていた。ぐるりとあたりを見回して、はっとした。左右前後、客席が埋まっている。私の前も後ろもいっぱいだ。朝焼けの色に人々の顔が赤らんでいた。ボサボサ頭のまま、起き抜けに慌てて出てきたというようすの男性。化粧もしないで取りあえず車に乗ったという女性。ここにいる観客たちは、ほとんど眠らずにアテネとエピダウロスを4時間もかかって往復してきていると思うと、私がおぜん立てした演目でもなんでもないのに感謝したくなった。

「ぴぃー」という笛の音が朝焼けの空に響いた。
「ぽん、ぽん」という太鼓の音も空高く上がった。
「翁」は豊穣を願う、めでたい芸能だ。能の演目の中でも最も古いもので、唯一舞台上で面をつけてはじめて神に扮して舞う。不思議と見ていると血が騒ぎ、エネルギーがみなぎってくる。次々と鳴り響く太鼓の音が耳から入って、脳の中心まで刺さっていく。ギリシャの乾いた空気は、楽器の音を空高くまで引っ張り上げてくれる。
川口さんも樋野ちゃんも、能を見るときに「寝てもいいんだ」といつも言っていた。睡魔に身をまかせながら、やがて眠気から醒める瞬間に見える景色が格別なんだと。太鼓の音と謡いの波に身をまかせながら、いつの間にか目をつぶっていた。薄いカーテンに包まれるような眠りは心地よかった。しばらくして、はっ、と目を開ける。すると今まで見えていなかったものが見えた。昨夜の公演では暗闇のなかで見えなかったけれど、ステージの背後に松の木々が茂っていたのだ。私は驚きのあまり愕然とした。日本の能舞台の背景と一緒だ。日本の能舞台の背景にはのっぺりと平面的な松の木が描かれている。それがエピダウロスの円形劇場のうしろには本物の松が生い茂っている。これはできすぎた偶然か、私たちが知らない芸能の原風景がここにあったのか。
太鼓のリズムに合わせて観客が思い思いに反応している。前に座っていた青年はまるでヒップホップでも聞いているかのように、裏拍を取りながら肩を揺らしている。日本の芸能に潜むグルーヴをギリシャの観客から教えてもらったような気持ちになった。
梅若玄祥先生による「土蜘蛛」は華やかで観客を魅了した。シテの手のひらから真っ白い蜘蛛の糸が空高く放たれると、一瞬、白い糸がその身体を隠した。その光景を見て、観客が感嘆のため息をついている。そうだよね、この美しさを共有できてよかったよ、と私は心の中で周りの観客に言った。
シテが去った舞台には、白い糸が散っていた。他でも見たことのある「土蜘蛛」の終わりだったけれど、ここでは糸がほんのりと黄色く染まっていた。ギリシャの太陽が顔を出し、また暑い夏の一日が始まろうとしている。