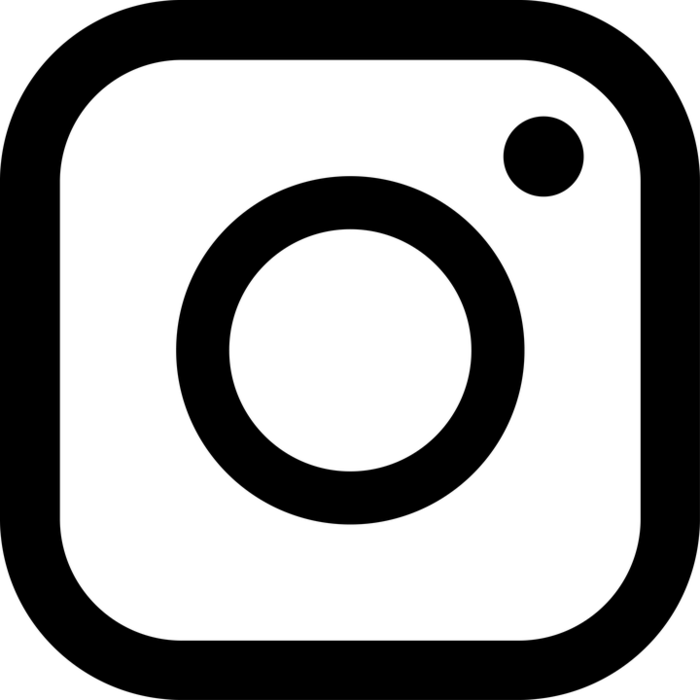空間現代の新譜リリースライブ、本拠地京都のライブハウス「外」にて。久々の暗闇、密室の人混み。その空気に慣れなくて、前座のDJがそろそろ長く感じ始めていたころ、終わりの気配とともに私の肩越しにごつい男性が彷徨き始めた。人混みを斜めに入ってきて、体を揺らしているのか、そうでないのかわかりづらいだけに気になって仕方がない。それが「何かが始まる」という空気に変わったのは、DJに背を向けて彼に顔を飛ばすもう一人の男性が現れてからだ。
空気が動いた。私と同じように状況を理解した観客たちが後退りする。満員の会場の真ん中に、あっという間にぽっかりと穴が開く。ゴツい男二人は相変わらず顔を飛ばしあいながら距離を縮めていく。そして肩だか、腕だか、身体が触れた瞬間、爆発した。殴り合いという名のコンタクト・インプロヴィゼーション。動きを人との接触で演出する、コンテンポラリーダンスのそれを思わせながらも、粗野な拳のやり取りに目を奪われる。前回、Contact Gonzoのパフォーマンスを見たのはもう10年近く前のことだろう。それも確か関西だった。その時、ああ、文化は関西で生まれていると思ったのを思い出す。
二人の男が掴み合う。そこにさらにゴツい背中の男が大砲のように身体ごとぶつかる。にじり寄り、ぶつかり、跳ね飛ばす。だけどそこには決定的に喧嘩ではない、三人の男たちのもったいぶった身体の揺れがあって、それぞれがぶつかり合いという名のコンタクトを求めている。「三つ巴」という言葉を表す肉体を私は今ここで見ている。
いつ何時、彼らの身体が丸ごとこちらに飛んでくるか、身の危険を感じながらも目が離せない。予測不可能にもかかわらず、コントロールされた殴り合い。ふと気がつくと音楽は空間現代による生音に取って代わっている。バチッ、ドスッという身体がぶつかる鈍い音にドラムとギターのリズムが鋭く重なり合う。感覚が脳を通過しないで身体のなかで増幅する。
なぜだか「自己責任」という言葉が頭に浮かんで、フッと消えていった。京都の外れ、バスの車庫前の小さなライブハウス。ここならば誰も追ってこない。知らない誰かが設けた野暮な規制にも捕まらず、やりたいことを好きなだけやってやろう。そういうところが世界の中心だ。境界は自分たちが決める。楽器の音と身体がぶつかり合う音が溶けあって、それを生み出しているアーティストも、聞いている観客も渾然一体となる。気がつくと自分の感覚が(意識じゃなくて)、演奏者の生み出すリズムを必死で取りに行っている。ドラム、ギター、ベースは土のなかに埋まった何かを探り当て、ひとつずつ掘り起こすようにリズムの塊を差し出す。乾いた身体はリズムを、心臓の音とシンクロするものを求めている。
「壮絶」という言葉が脳に現れては消えた。大抵、その言葉の後には問い返しのつかないような結果が待っている。だけどここに悲観はない。会場にいる人間それぞれの身体が脳をすっとばして、生な何かを追いかけている。生きようとしている。まだ「壮絶」という言葉が後を追ってくる。言葉は遅い。言葉はいつまで経っても正確に目の前で起こっている出来事を表現できない。
翌日、朝起きるとくるぶしが痛い。そういえば、昨日、暗闇のなかでぶつかり合って飛んできた男の石頭が私の足元を直撃したのだった。世界の中心は確実にそこにあった。それはどうやら、本当のことだったらしい。