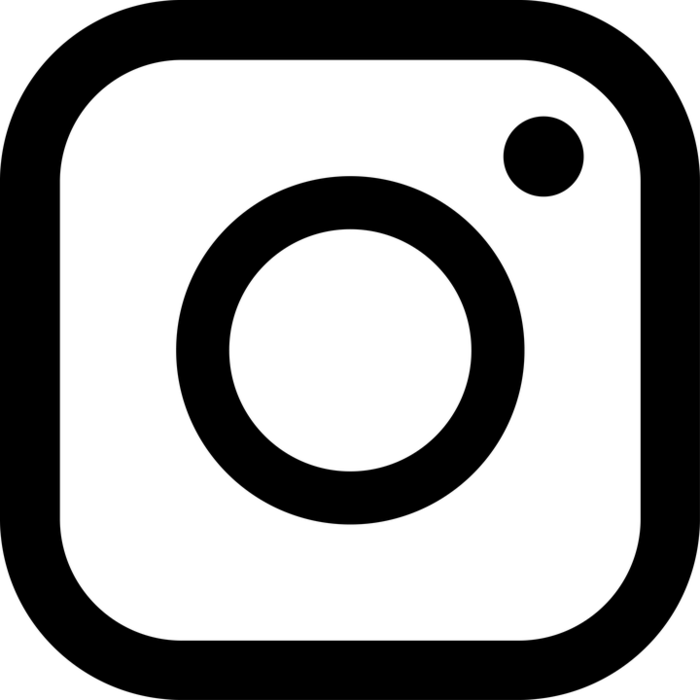・ フェルナンド・カサセンペレ
青い目の男はそびえるように背が高く、首から肩、背中にかけては筋肉で覆われている。とにかく手が大きくて、いくつもの擦り傷が積み重なった頑丈な手袋のようだけど、握手をした感触はなぜか柔らかく、なにしろ雄弁だった。アトリエにはサンティアゴのチリ国立美術館で行われる個展に出展する作品が一同に集まり、搬出を待っている。
「作品がたくさんある時ではないと、ここに来て欲しくないんだ。空っぽのアトリエを見ても仕方ないから。」
そう言いながらひとつひとつの作品に触れ、その規模の割には小さなアトリエを歩き回る。久々に近くで見る成果物の数々にむしろ本人が興奮しているようだった。
・ アトリエ
そこはまるで鉱物の採掘所のようだった。床から壁から天井まで土で覆われていて、窓から差し込む穏やかな光の中に土埃が舞っていた。床には泥水が溜まったバケツや乾かないようにビニールをかぶせてある粘土がいくつも置いてあって、足の踏み場もない。
土にまみれた壁には、埃と湿気でふにゃふにゃになった写真が貼ってある。そのうちの一枚はレンガを積み重ねて作ったアーチの写真だった。フェルナンドはその写真を見ながら、どうやって古代の人間がこのいかにもシンプルで美しく、効率的な造形を編み出したのか、と問う。先人が投げかける課題に心底胸躍らせながら、そうやっていつまでもその写真について語っている。

・ 作品
陶器でできた作品は様々な表情をしている。真っ白い土の中に、コバルトや銅が練りこまれているもの、陶器の削りかすをぎゅっと固めたもの、手で粘土を動かした痕跡が堂々と残っているもの。いずれも塊の中に、色と素材感が自由に遊び、柔らかさと硬さが同じ瞬間に出会って混じり合っている。粘土の柔らかさを連想させるぐにゃりと自在に曲がった作品は、その運動がどこまでも続くように力強く、見ていて気持ちがよい。
アトリエの隅に寄せられているキューブ状の作品は、ココナッツのかけらのようなふわりと空気を含んだようなもので覆われていた。フェルナンドは、大股でその作品に近づくと、上にかぶさっている埃っぽいビニール袋を捲り上げ、背中と腰に力を入れて展示台ごと引きずり出した。柔らかく優しい印象の造形を裏切る重量。
「この下にキャスターを付けるっていうアイディア、素晴らしいんだ。ほんの2、3 年前に思いついたんだけど、世界が変わったようだよ。それまではひとつずつ作品を持ち上げて移動していたのだから。救われた。」
・ チリ
チリは土から生まれ、土で生きる国だ。15世紀にヨーロッパ人が入植する前は先住民による土と石の文化で栄えた。そして今はその鉱山資源を世界に輸出し、銅の輸出国としては世界一である。一方、この実績がもたらす荒れ果てた採掘場の存在を知る人は少ない。輸出価値のある鉱物だけが掘り起こされて、使い物にならない残留物が残った土地は次々と砂漠になっていった。フェルナンドは90年代から、鉱山に残った土のリサーチを行い、それを他の陶土と配合し作品を作っている。彼のアトリエの壁には丁寧に作られた棚があって様々な色調の陶片が並んでいる。それは作家が陶器の彫刻を作る際に参考にするカラーパレットであると同時に、砂漠の破片でもある。彼はこうして使用価値がなくなった土を作品に昇華する。
・ 土
フェルナンドは自分が住む土地の土にこだわる。97年に拠点をチリのサンティアゴからロンドンに移住するときには17トンもの故郷の土を持ってきた。いや、それではロンドンを拠点にした意味がないということで、移住してからはロンドンで土を手配するのだが、実際、手元に届く土はどれもヨーロッパ各地からやって来る。こうして、フェルナンドは知らぬ間に土が世界各国を移動しているということを実感する。
アトリエの小さな棚に並んでいる異なる色と形の陶片は、まるでどこかから発掘してきたような古い土の塊のようだけど、これこそがフェルナンドの作品を雄弁にするボキャブラリーである。彼は異なる種類の土を掛け合わせて、無限の土の表情を引き出すために地道で果てしないトライ・アンド・エラーを繰り返す。彼の信じる定理はこうだ。地球の土である限り、すべての土は混ざり合い、ひとつの塊となり、そして地球に還る。


・ サマセット・ハウスとアントファガスタ砂漠
2012年、フェルナンドはロンドンのサマセット・ハウスの中庭を陶器の一万本の花で覆い尽くした。期間限定のアートプロジェクトを依頼された彼は、仰々しい野外彫刻を置くのではなく、人々が入り込む余白を残しながら、空間を土の塊で埋め尽くすことを選んだ。
一輪の花は二つとして同じものがなく、その表面は赤茶色の銅で覆われている。制作はすべて一人で行った。まず白い土の塊にチリの砂漠から運んできた残留物の銅をかぶせ、一つ一つ棒で叩くことで、ふんわりとした形の花の部分を作った。そして、それに鉄の茎を取り付け、抽象絵画の中に現れるような花にする。一週間で二百本から三百本。二年間かけて一万本。陶器の花はしばらくロンドンのアトリエを占領した。
この一万本の花を設置するために、いつもは石畳で覆われているサマセット・ハウスの中庭にトラックで土が運び込まれた。そして芝生が敷かれ、芝生に水をやるためにスプリンクラーが設置された。それからドリルを使って鉄と陶器でできた花が芝生に埋めこまれると、一万本の花は波打つようなリズムで緑の上に点々と色を蒔いた。やがて花と緑はみずみずしい空気を招き、それが虫や鳥を招き、すると近隣の人々が夏空の下、ピクニックにやってきた。そうしてあらゆる生命をロンドンの中心地に招いた。


その三年後、プロジェクトは最終形を迎える。この一万本の花はチリに運ばれ、北部のアントファガスタという鉱山に植えられた。この場所こそ花を赤茶色に彩った銅の採掘地。人間が作った砂漠に打ち捨てられた残留物の銅は、花の表面を彩り、故郷の土地を讃えるために戻ってきたのだ。
・ 衝突と混合
フェルナンドは土を通じて国を超え、あらゆる地球の肌に関わりあう。そして土や石、陶器あるいはレンガを通じて、先人の文化を掘り起こし、人間が行ってきたトライ・アンド・エラーを今も続けている。こうしてフェルナンドは縦と横の糸を紡いでいくように、素材を通じて地理的な境界を超え、手を通じて過去と現在を行き来する。それはある時突然、文化の衝突と混合を見た南米の足跡そのものを体現しているようだ。
彼の創造力は土が教えてくれる知識を糧に大きくなる。そうして生まれた作品は限りなく自然そのものに似つかわしいので、再び自然に戻っていく。その行為そのものが人間の営む文化を讃えているようでもあり、反対に自然の循環を力まかせに閉じてしまおうとする人間の愚かさを明るみに出しているようでもある。しかしながら、フェルナンドはそんな壮大なテーマを主張するわけでもなく、ただずしりと重い陶器の塊を大きな手のひらに抱えて言うのだ、「ここにすべてがある」と。