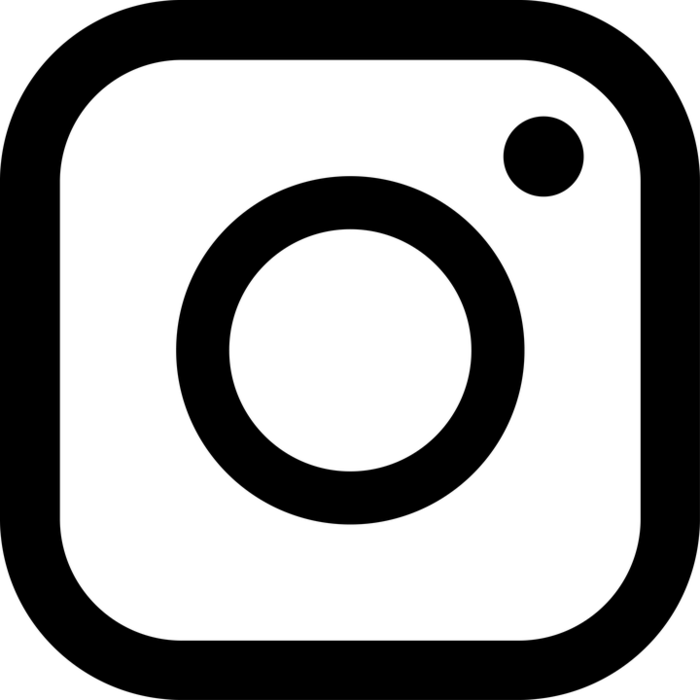それは確か暑い夏の日ではありましたが、そのバーの中はこぢんまりとしていて薄暗く、蝋燭が灯っていたような場所だったので、今思うと、それは寒い冬の夜だったような気もします。
私は、その日久々にある男性と再会したところでした。その人に近況やらなにやらを話したあと、私はずっとその人に聞いてみたかったことをたずねました。
ブルース・チャトウィンってどんな人だったんですか?
「チャトウィンか。昔、その辺で会ったんだよ。」
その人はそのバーの中にあった唯一の窓の向こうを指差して言いました。窓の外には薄暗い路地を白い街頭がぼんやりと照らしていました。
ブルース・チャトウィン。名門サザビーズの美術品鑑定士を若くして辞めたあと、考古学を学び、世界各地を旅したイギリス人の作家。
「ちょうど、彼が中国からアメリカに渡ろうとする途中でね。日本に寄って、自分の本が訳されるというんで、その様子を伺いに来たんだ。僕は、彼の本をこれから訳そうかというところだったけれど、実は何も手をつけていなかった。しかも、そのとき僕は彼について、ほとんど知らなくて。そのころ、神田の東京堂っていう本屋さんの洋書コーナーで偶然彼の本を見つけたんだ。当時、その洋書コーナーを担当していたおやじがすごくよいセンスをしていて、その本棚一個分のセレクションが、もう、ものすごくよかった。今で言えばキュレーターだよね。もう、彼はいなくなっちゃったから、今はどうかわからない。そういうわけで、そこで手に取ったのが、ブルースの一冊。一文が短くコンパクトで、これなら僕にもできるかもって思ったのが本当のところ。」
その人はまるでゼンマイがゆっくりと運動しているように話しました。ゼンマイを巻きあげているときは沈黙し、思考し、それを解き放つと同時に一定のペースでよどみなく話しはじめるのです。
「チャトウィンとはその辺の居酒屋で飲んだよ。SAKEがおいしい、とかなんとか言っていたな。彼、地理学や歴史にむちゃくちゃ詳しい。そのときは確か、ロシアにはまっていたな。」
チャトウィンの有名な著作のなかに『パタゴニア』という作品がありました。それは彼がアルゼンチンの南端のパタゴニアへ旅に出たあとに創作した小説です。
「なぜパタゴニアに行ったかって?彼は日本の俳句にも詳しいんだけど、芭蕉の「奥の細道」も読んでいた。その、「奥の細道」の英訳がThe road to the northって、いうらしい。そこで彼は、芭蕉が北にいくんだから、僕は南に行こう、ずっとずっと南に・・・・、と思ったみたい。
ただ、南でも、なぜパタゴニアに行ったかっていう理由付けが本当に納得いってしまう。子供のころ、彼のお祖母ちゃんがある動物の皮片を持っていた。それが何かって母親に尋ねたら、それは南米のパタゴニアっていうところに生息していた恐竜のものだって言ったとか。その話が彼のなかでずっと生き続けていて、それをつきとめるために行ってみた。こんなことが、彼の持っている小さな黒いノートの最初の表紙にびっちり書いてあるんだ。それを、読んでいくと、これは行かざるを得ないよなあ、って思ってしまった。
帰る段になって、チャトウィンと僕は地下鉄のホームまで一緒に歩いていった。地下鉄のホームで電車を待っていると、チャトウィンが僕に突然、君は何をやっているんだ、って質問した。
『僕は地域計画をやっている。それで、バックミンスター・フラーが好きで、その訳書も出したことがあるんだ。』
『バッキーか。バッキーには一度会ったことがある。』
その瞬間、電車がチャトウィンの前に止まって、彼はそれに乗り込んだ。
『バッキーのことなら、たくさん話したいことがある。』
って、言葉を残したところで、電車のドアが閉まった。
言いたいことって、何だろう。
彼の悲報を聞いたのは、奥さんからで、彼が本国のイギリスに帰ってからのことだった。
中国のミイラに備わっている疫病に感染したとか、エイズだったとか、本当の原因はわからない。
でも、今でも、バッキーについて言いたいことって何だろうって考えるんだ。知りたい気持ちでいっぱいだからこそ、チャトウィンは今でも僕の心のなかで生き続けている。」
何年かの月日が経った今、もう一度その人の話を思い出してもなお、私とはゆかりのない異国の芸術家の存在が生き生きと目の前に現れます。死者は唯一、生者のくちびるをもってこの世に甦り、さらにそれを伝って、生前は会うことのなかった人々との出会いを果たすのでしょう。